昨日、八十二銀行と長野銀行の経営統合が認可されました。
八十二銀行のホームページでは、「基盤的サービス維持計画」(→経営統合により発生するおそれのある不当な不利益、すなわち不当に高い金利・不当な保証条件の悪化等を防止するための方策)の内容を確認することができます。
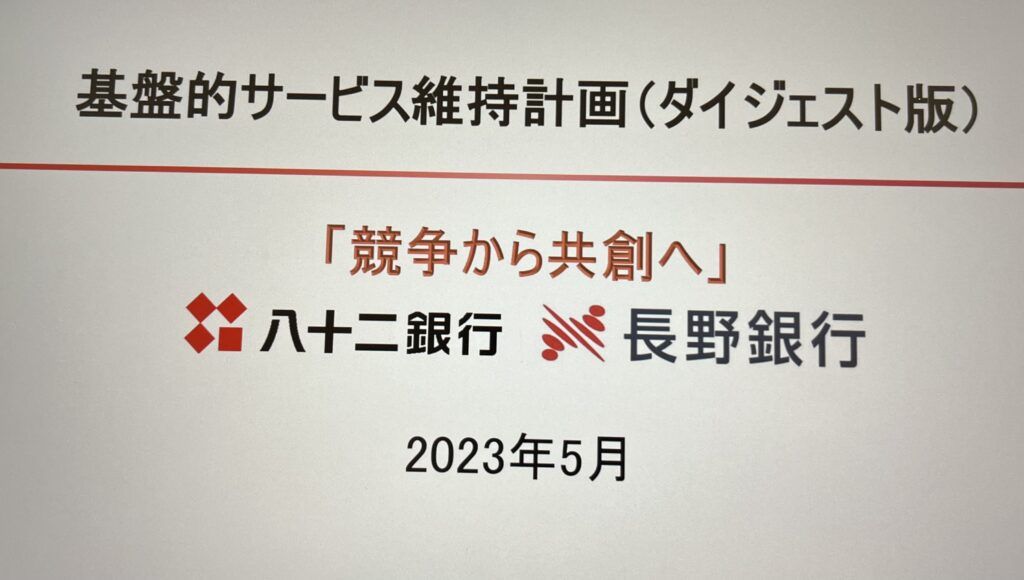
https://www.82bank.co.jp/file.jsp?id=release/2023/pdf/news20230529.pdf
29日の日経電子版にある通り、
~長野県内の貸出金シェアは、合計で6割を超え、強い影響力を持った「ガリバー地銀」となる。両行はモニタリング体制の整備や社内周知を通じて、不当な貸出金利の上昇や保証の取得、貸し渋りが生じないよう取り組む考えだ。(記事より)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC24CPS0U3A520C2000000/
なのですが、ワタシ自身はこの点については大きな懸念を持っていません。(長崎の場合にはこだわりましたが)
長野県は他県と比べ、それぞれのエリアを守る信用金庫のネットワークが強く、シェアへの執着だけしか見えない信用金庫がある一方で、
エリアによっては業況が悪くなり銀行の足が遠のいた企業を信用金庫が再生する事例も少なくありません。
規模的制約や機能面での弱さから信用金庫では十分に対応できないことはあるものの、商工中金等との連携の中でそれをカバーするやり方は上手くいっていると考えられます。
さて、
ワタシが注視しているのは、ダイジェスト版・8ページにある「人的資本の活用」のところです。
経営効率化により捻出した人材をソリューションやデジタルなどの戦略部門に再配置するという趣旨です。
両行トップは経営統合の発表段階からこの点を言及しています↓が、
いままでの地域金融機関の合併事例では、ごく一部の例外を除き、この再配置に苦労しているように見えます。
長野県のガリバー地銀の経営手腕に期待します。



